
自然破壊や環境問題に興味があって読書を進めていた私は、ある時、自然破壊の元凶が近代哲学の祖として名高いデカルトにあるという言説を知ったが、その事実は私にとって俄かには信じがたいことであった。デカルトと私たちの間には400年弱の時間経過が存在するから、認識の相違がみられるのは当然であるのかもしれない。しかしその事実を鑑みても、現代を生きる私たちの目には、「自然は機械のようなものだから、森林伐採や環境汚染などの自然破壊をしても権利上大きく問題視されない」という論理は短絡的に映る。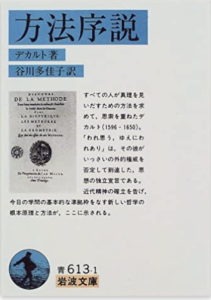
今日問題視される自然破壊の一因は、人間中心主義的な機械論的自然観にあると言われている。例えば、哲学者の谷川によれば「機械論的な自然観はヨーロッパでは主流になり現代につながり、それを自然破壊に結びつけたりする見方」があり、また「こうして自然が、科学技術によって人間に征服され、その進歩とともに汚染や破壊をもたらす」と言われることもあるという(谷川, 2014, p.145)。つまり、機械論的自然観における、自然は機械の部品のようなもので人間の欲望を満たすための手段であるという考え方が、自然をこれまで破壊してきたのだということである。そして、その自然観は、デカルト的自然観との異名を持つ通り、フランスの哲学者ルネ・デカルトによって生み出されたのだという。
そこで私は、デカルトの思想が本当に自然破壊へ拍車をかけるものであったのか、自分自身の手で確かめてみたいと考えた。本稿では、彼の著書『方法序説』を適宜参照しながら、「デカルト的自然観」を捉えていきたいと思う。
哲学者の谷川によれば、「ベイコン、デカルトを出発点とするヨーロッパ近代の自然観の哲学的な基礎」にあるのは、『方法序説』第六部における次の表現である(谷川, 2014, p.145)。それは、「(自然にかんして得た知見がデカルトに理解させたのは、)われわれが人生にきわめて有用な知識に到達することが可能であり、学校で教えているあの思弁哲学の代わりに、実践的な哲学を見いだすことができ、この実践的な哲学によって、火、水、空気、星、天空その他われわれをとりまくすべての物体の力や作用を、職人のさまざまな技能を知るようにはっきりと知って、同じようにしてそれらの物体をそれぞれ適切な用途にもちいることができ、こうしてわれわれをいわば自然の主人にして所有者たらしめることである」というものだ(デカルト, 谷川訳, 1997, p.82)。
名古屋大学の山田によれば、この文章は、「フランシス・ベーコンの思想(知と力は合一し、自然にしたがうことによって自然を征服する)の影響があると考えられている」(デカルト, 山田訳, 2010, p.250)。つまり、ベーコンは『ノヴム・オルガヌム』において、自然の征服には、自然に素直にしたがうことで原理や法則を発見することの重要性を説いているのである。以上の文章を読むと、デカルトとベーコンが人間中心主義的な機械論的自然観をもっていたというのはやはり真実であるように思われる。しかしその解釈は本当に正しいのだろうか。
デカルトの文章をより深く読み解いてみよう。「自然の所有者」という表現のみから、デカルトが機械論的自然観を持っていたと結論付けるのは早計である。ここで、より厳密な解釈を行うために『方法序説』の原文を参照する。「自然の主人にして所有者」とは、原文では「les maitres et possesseurs de la nature」と記述されている。注目しなくてはならないのは、デカルトが、「de la nature」に対して、「les maitress」=「主人」と、「possesseurs」=「所有者」を、等位接続詞etを用いて並列して記述している点である。等位接続詞とは、読んで字のごとく「等しい位の言葉を結ぶ接続詞」であり、英語では「and」などがこれに当たる。つまり、『方法序説』の日本語訳を見る限りでは「主人」よりも「所有者」に重点が置かれているかのように感じるが、実際にはそれらは等位なのである。したがって、私たちは「自然の主人」という表現についても注意深く読み解く必要がある。
まずは「主人」という語が何を意味するのかを考える。それは主に、使用人の雇い主を意味する語である。ここで、使用人と主人の関係は、一方向的ではなく、双方向的であることに注意したい。そこには、使用人は主人に対し奉仕するが、同時に主人は使用人に対し何らかの報酬を与えているという雇用関係を見出すことができる。加えて、主人は使用人に対し比較的優位に立ってはいる一方で、絶対的優位に立ってはいないことも重要である。主人が使用人を酷使し健康を害する行為は、使用人の尊厳を侵害する行為として社会的に許容されず、たとえ主人が使用人の尊厳を一切考慮しない極悪非道な人物であったとしても、使用人の雇用環境が劣悪であるならば、使用人は主人のもとを去るため、雇用関係は成立しない(もしそれさえもできないようであれば雇用関係ではなくて奴隷関係と言うべきであろう)。
つまり、主人という語は、使用人による自身に対する奉仕を継続させるために、使用人が奉仕を続けられるだけの環境を整備する義務を背負うということを暗に含む語なのである。この含意は現代的解釈だけでなく、デカルトの時代にも適用しうると考えられる。
ここから、「主人」という語を使用したデカルトと、「征服」という語を使用したベーコンの自然観の差異を読み取ることができる。ベーコンのいう「征服」を、征服者と被征服者に分割して捉えると、その二者の関係に、先に挙げた主人と使用人の間にあるような双方向性は見られない。征服者は被征服者に対し存在の抹消を含むあらゆる行為を行う可能性があり、征服者は被征服者に対して絶対的優位に立っているからである。
では、改めて「自然の主人」という表現を検討する。これまで検討してきた主人という語の意味を踏まえると、「自然の主人」とは、自然のもたらす恩恵を享受することができる一方で、自然による恩恵を継続的に享受するために、自然が恩恵をもたらすことができるだけの環境を整備する義務を背負っている者を意味する。その義務を放棄すれば、自然による恩恵を享受することはできない。『方法序説』第六部における「果実」という比喩を用いるならば、「人間は、果実を継続的に得るためには、果実が育つために必要な最低限の自然環境を用意しなければならない」ということができる。したがって、デカルトは、一般的に想起されるような人間中心主義的な機械論的自然観を持っているとは必ずしも言えないという解釈も成り立つことがわかる。
以上のように、本稿では、デカルトが、『方法序説』第六部にて、「所有者」という語に加えて、「主人」という語を使用したことから、彼のもつ自然観においては、自然による恩恵を継続的に享受するためには自然環境を整備する必要性があるという解釈を提示した。したがって、この解釈が成立する限り、今日問題視されている自然破壊はデカルトの意図するところではなく、自然破壊の一因をデカルトに求めるのは誤りであろう。
《参考文献リスト》